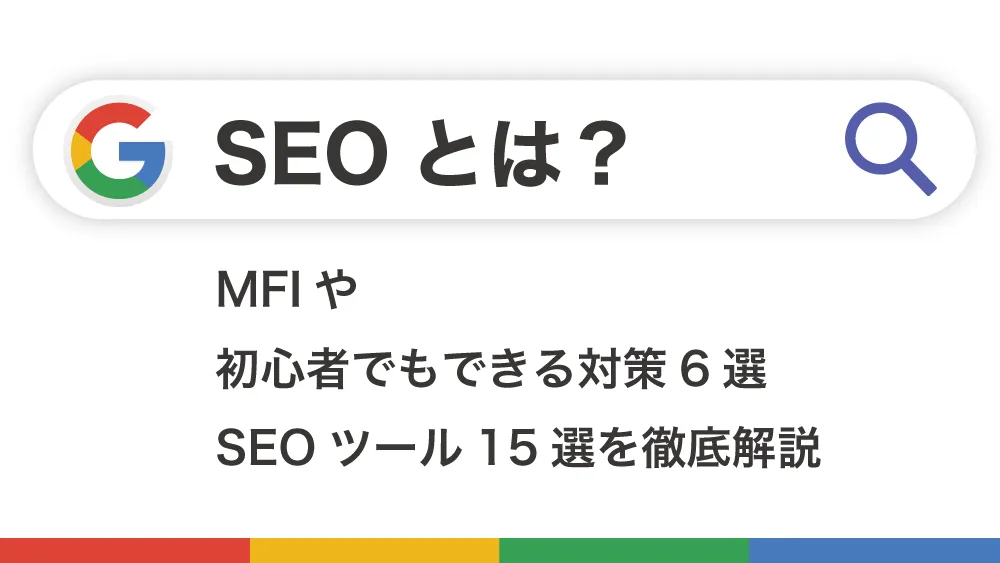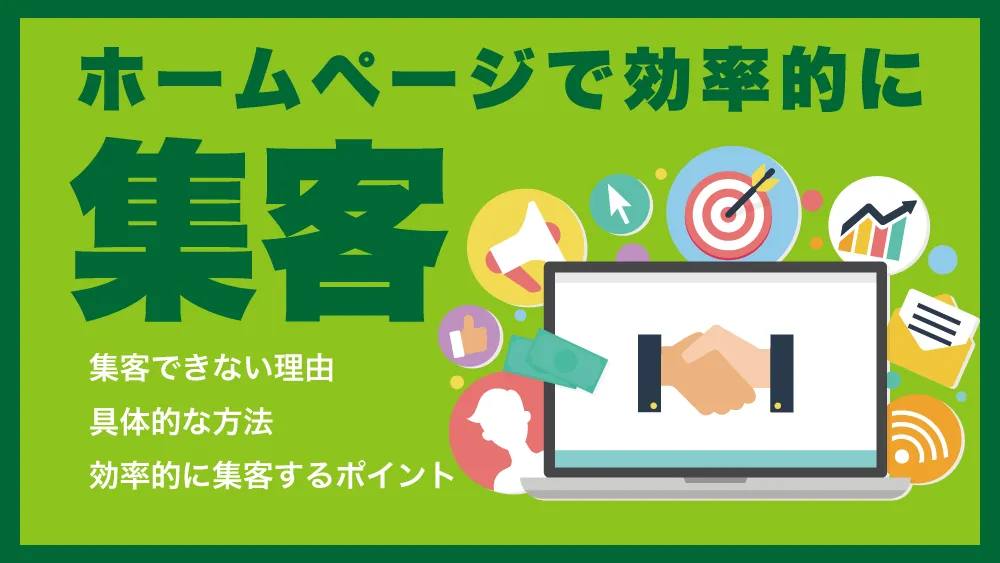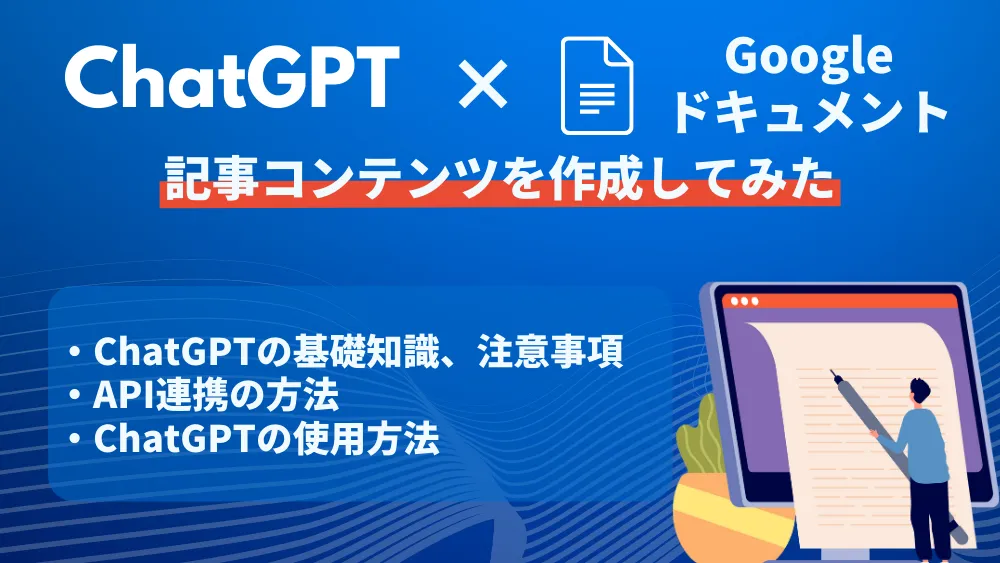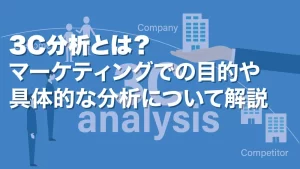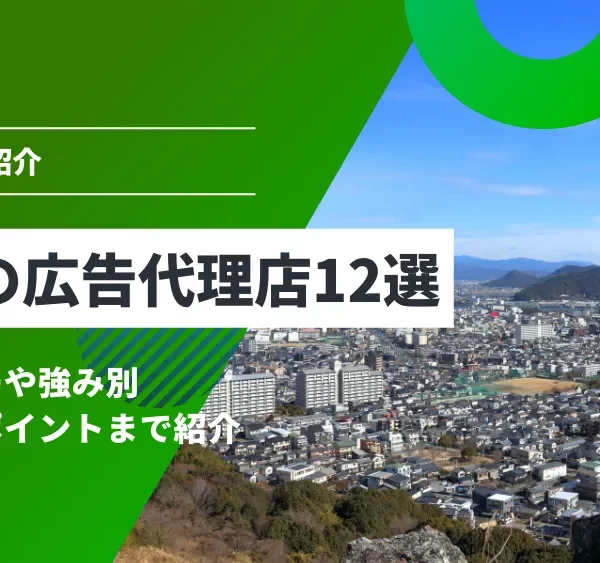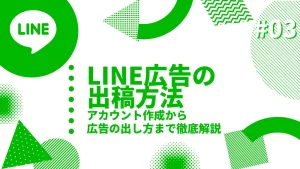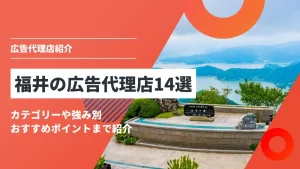営業活動を行なっていて、1回のコンタクトで成約できたり、案件化して進んでいったりすることは少ないです。
そのため、後追いをしていかなければなりません。
顧客には、明確に導入時期が決まっている顧客もいれば、特に決まっていない顧客もいます。例えば、ITツールの導入で営業活動を効率化していきたいという顧客のヒアリングをしていったら、効率化したいことは本当だがいつまでに効率化したいのか、そもそもの本質的な課題が定まっていないなどの顧客に関しては、導入予定の時期が全く決まっていないため、顧客から問い合わせがきたものの案件化しないケースが多いでしょう。
上記のような顧客も多いため、初回のコンタクトから成約に繋がるまで数ヶ月以上かかります。その間コミュニケーションを続けていかなければ、導入しようと思った際に自社のことを忘れてしまっており、成果に繋がらないということが多いです。
営業活動における業績を継続して向上させていくためには、案件化している見込み顧客だけでなく、上記のような長いスパンでの見込み顧客もしっかりとフォローをしていかなければならないのです。
今回の記事では、営業の後追いメールをメインに紹介していきます。例文やタイミングなどについて解説をしていきますので、ご活用いただければと思います。
顧客フォロー(後追い営業)については、下の記事で解説をしておりますので合わせて御覧ください。
参考:営業フォローは重要?営業フォローの正しい方法と重要性について解説
営業における後追いとは?
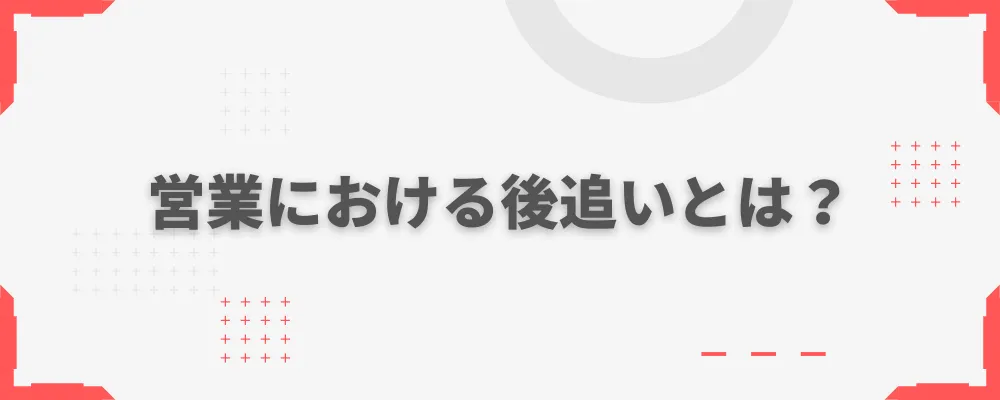
営業活動における後追いには、主に2つの種類があり、「リードへの後追い」と「商談を行った顧客への後追い」です。
リードへの後追いは、営業活動やマーケティング施策で集客したリードと定期的にコミュニケーションを取ることにより、関係を持続させ将来的な顧客化を目指して行います。
商談を行った顧客への後追いは、提案内容の検討状況の確認や説明の補填、不安点の払拭を行うために行います。
後追いの方法は、いくつかございます。
- 訪問して後追い
- 電話での後追い
- メールでの後追い
- WEB会議システムを活用して後追い
特に、メールは電話よりも、抵抗感を感じる人が少なく、幅広いシーンで使うことができるツールとなります。そして、電話はメールより抵抗感を感じる人が多いものの、顧客との距離を縮めてくれるツールとなります。
そのため、営業フォローは基本的に電話とメール、時々SMSなどをうまく組み合わせながら行っていくと良いでしょう。
今回は、後追いメールについて詳細を解説していきます。
営業の後追いメールにおける種類
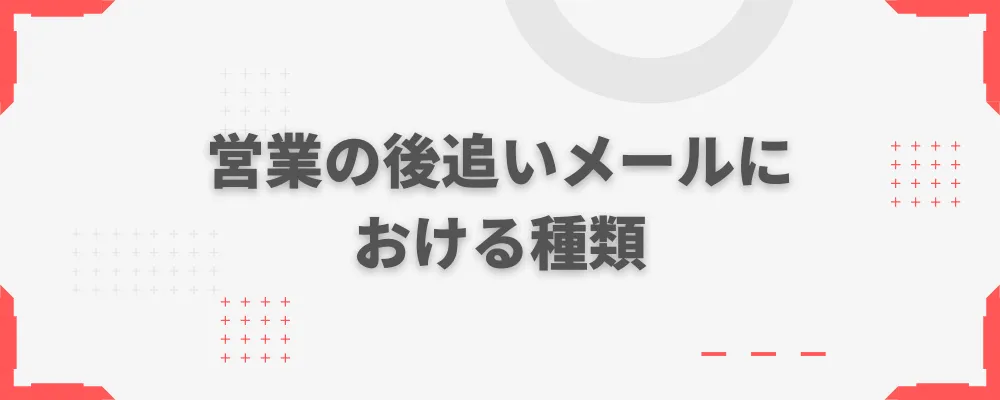
後追いメールですが、幅が広くなってしまいますので、今回解説をするメールの定義は「商談を行った顧客への後追いメール」とします。商談したものの成約できなかった顧客への後追いメールです。
その定義での後追いメールでは、下記の3種類に分類されます。
- 商談終了後すぐに送る後追いメール
- 案件が進んでいない顧客への後追いメール
- 失注した顧客への後追いメール
それぞれ解説を行っていきます。
商談終了後すぐに送る後追いメール
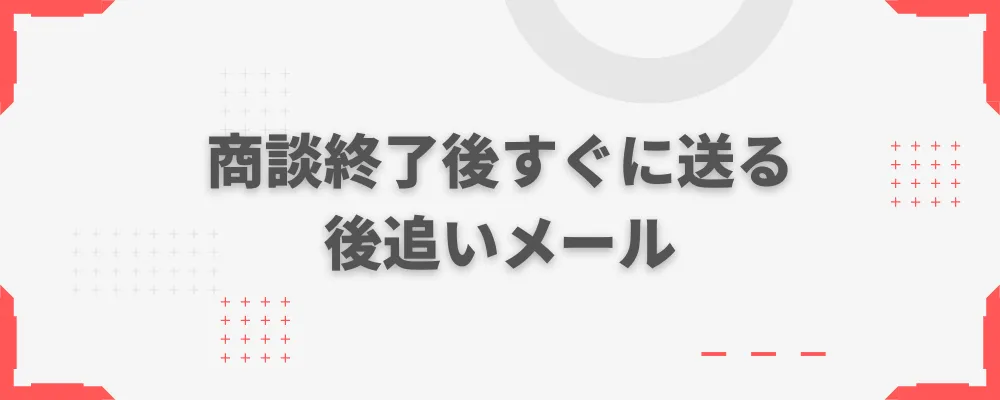
商談が終了してからすぐに送る後追いメールは、皆様お送りしているかと思いますがお礼のメールとなります。
ですが、ただのお礼のメールだけではなく、顧客の購買プロセスを進められるように工夫をすることが良いです。
商談終了後すぐに送る後追いメールで送るメールの内容
商談終了後すぐに送る後追いメールで、顧客に送るメールでは、下記の5つを記載して送りましょう。
- 次回の商談などのアクションについて確認
- 商談内容の要約
- 商談で聞かれた質問の回答
- 提案資料・共有資料の送付
- その他商談中に触れたサービス・商品について
この中で重要となる点は、「次回の商談などのアクションについて確認」になります。
今回の後追いメールは、成約にならなかった顧客へ送るメールですので、「“いつ”までに・“どのようなこと”をするか」をすりあわせて、合意を取っておきます。
例えば、下記のような内容の合意を取りましょう。
- 次回の商談・打ち合わせはいつ行って・誰が参加するか
- その次回の商談等で準備するものと準備する人
- 社内検討はいつまでかかる予定か
- 検討が終了したタイミングで自社から連絡していいか
- 稟議や決裁に対して自社でご支援できることはあるか
ここまで決めますと、顧客の購買プロセスを進めることができます。
ただ上記の内容のすり合わせに関しては、メールで行うと時間がかかったり、手間がかかったりしてしまうため商談中(成約できないと判断した際)に行いましょう。
その決めた内容をメールで再確認をすると良いです。
商談に同席されていた担当者へと展開する方法
昨今では、新型コロナウイルスの影響により、オンライン商談が広がっております。
オンライン商談には、多くのメリットがありますが、反対に出席された方の情報を得にくいというデメリットも発生してしまいます。
例えば、オンライン商談で初めて接触した担当者の名前や連絡先、名前の名乗りがあったものの漢字がわからないなどです。
オンライン商談を行っている営業マンはこのような経験をしたことがあるのではないでしょうか?
そのような同席されていた担当者へ後追いメールを送る事ができませんので、連絡先がわかっている担当者の方へ「ご同席されていた〜〜様(名前不明の場合は皆様)へもお伝えいただければ幸いです。」と記載して送りましょう。
そうすると、多くの方は同席されていた担当者をCCに加えて返事をくれます。
CCから情報を収集できましたら、今後アプローチが必要になった場合に活用できるでしょう。
追伸テクニック
意外と活用できるのが、「追伸」です。
追伸がついているメールを受け取りましたら、ついつい読みたくなる人も多いでしょう。
更には、追伸ではビジネス以外の会話もしやすいため、活用されていない営業マンは使ってみましょう。
追伸に記載する内容については、以下のような内容が良いです。
- ビジネス以外の内容(アイスブレイクで話した内容や顧客の詳細情報/出身地・趣味など)
- 顧客の部署にとって価値がある情報共有
- 企業で活用できる価値ある情報共有
このような追伸を送ってくる営業マンはいませんので、少しの差別化をすることができるでしょう。
商談終了後すぐに送る後追いメールの例文
それでは、商談終了後すぐに送る後追いメールの例文を紹介致します。
顧客情報を追記、自社の内容に合わせ変更してご活用ください。
株式会社〜〜〜
◼️◼️様
お世話になっております。
株式会社Value Betの□□でございます。
本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。
ご同席していただきました◆◆様にも、お礼をお伝えいただければ幸いです。
〜日までご検討されるということでしたので、
改めて◼️◼️様へお電話(メール)させていただきますのでご連絡致します。
それと、ご質問の〜〜については、社内で確認後○日までにメールにてご連絡致します。お待たせして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
その他、ご不明な点やご質問事項などございましたら、
お気軽にご連絡いただければと思います。
また、今回お打ち合わせで共有した資料を添付しておりますので、
ご検討の際にご利用いただければ幸いです。
引き続き今後ともよろしくお願い致します。
追伸
◼️◼️様がおっしゃられた、〜〜について社内で確認したところ◼️◼️様と同じ出身地の社員も使っているとのことでした。私も今度、ネットなどで買ってみようと思います!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社Value Bet
───────────────────
□□ □□
〜〜〜〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
案件が進んでいない顧客への後追いメール
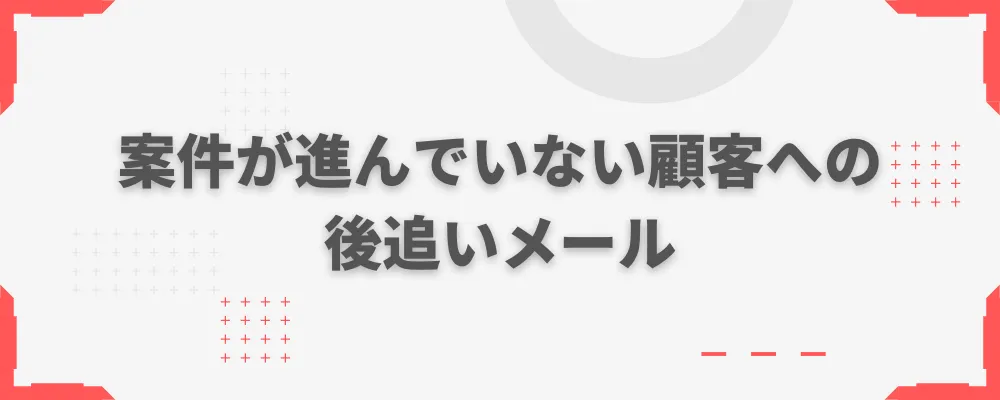
続いて、案件が進んでいない顧客への後追いメールについて解説を行っていきます。
止まっている顧客への後追いメールで活用すべき3種類の内容
案件が進んでいないということは、顧客から連絡が返ってこない場合となります。
この際に、メールの内容は「連絡の催促」等になると思いますが、伝え方を間違えたら悪い印象を与えかねません。
そのため、催促するためにメールを送るとしても、忙しい顧客に対してサポートさせていただくというスタンスでメールを送るようにします。
そこで活用できる内容を3種類紹介致します。
①検討状況について確認
ご検討の状況についてはいかがでしょうか?
その他にも、ご不明点・ご不安点などございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
②追加情報の提供
以前、お伝えいただきました〜〜(課題)について、
弊社で改善できた事例がございましたので、一度ご確認いただければと思います。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
③期限に沿った確認
〜〜様、以前お打ち合わせさせていただいた際に、
□□日頃に検討が終わりそうと言われておりましたので、ご連絡いたしました。
その後のご検討はいかがでしょうか?
ご多忙だと思いますので、何かございましたらご連絡いただければと思います。
いずれも、お気軽に〜などで少し言葉を柔らかくして伝えていくことが良いです。
そうしないと、相手も催促だと思ってしまい、印象が悪くなってしまいます。さらに顧客との関係性によって、より砕けた文章でも良いと思いますので、カスタマイズしてご利用いただければと思います。
断りづらい為連絡していない顧客もいれば、本当に忙しくて連絡できていない顧客、忘れていた顧客もいますので、相手が責められているなど感じないよう言葉を選んで連絡すると良いでしょう。
案件が止まっている後追いメールを送るタイミング
案件が止まっている顧客への後追いメールを送るタイミングは、商談を行っている最中に合意を取っておくと良いでしょう。
そのタイミングは以下を参考にしましょう。
- 稟議・決裁の終了するタイミング
- 社内での提案結果がわかるタイミング
- 相見積もりの提案が終了するタイミング
これらの日時で再度連絡していいかを確認しておきましょう。
ただ、注意点もございます。
それは、この合意を得る際の言葉を間違えたり、伝え方を間違えたりすると相手は「おまかせする際にはこちらから連絡します」と断ってくる場合もあります。そのため、しっかりと関係性を構築していたり、しつこくないように合意を得たりする必要がありますので注意しましょう。
メールのあとに電話する
メールを適切なタイミングで送ったあとに、返信が返ってこない場合もあるでしょう。
その場合は、必ず電話でも連絡を取ります。
というのも、メールでは伝えられないような内容の場合もあるからです。
例えば「上司の〇〇さんが導入に反対しだした」や「他社のほうが安いため他社を導入しようか考えている」などです。
メールでは言いにくい・伝えにくいことでも、電話であれば話してくれる可能性は高くなります。そして、その状況が把握できた場合、違ったアプローチを可能とするのです。
例えば、上司の反対している理由を聞いた上で解消できるよう打ち合わせをしたり、競合他社の商品・サービスを検討している理由を踏まえもう一度提案したりなど、次のアクションに進めることができます。
失注した顧客への後追いメール
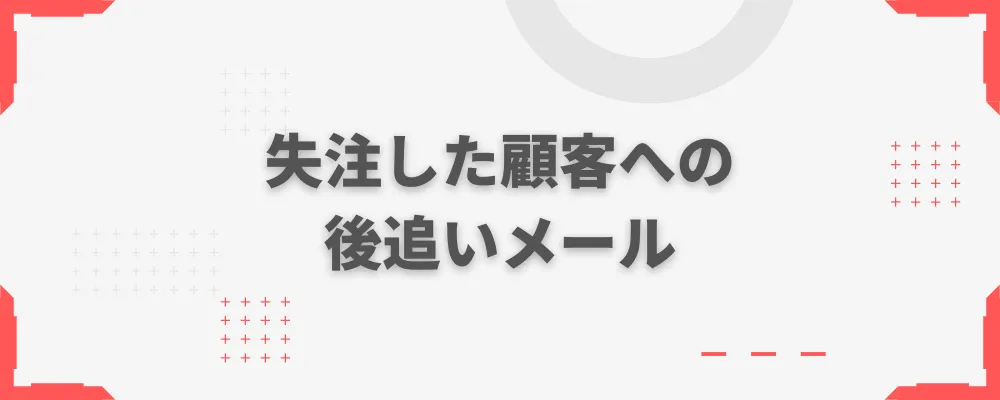
商談して失注してしまった顧客への後追いメールは、掘り起こし営業とも呼ばれており、ここでは、その掘り起こし営業のメールについて解説を行っていきます。
失注した顧客への後追いメールが重要な理由
営業マンが最優先する顧客は、現段階で進行している案件です。
そのため、失注した顧客への対応やアプローチは見落とされる事が多いですが、一度は検討してもらえた顧客となりますので、再度アプローチをしていくことで、成果へ繋がる可能性は高いです。
失注した顧客は、競合他社で導入している場合とまだ検討しており導入していない場合、そもそも導入しないことが決まった場合と3つのパターンが考えられます。
米国のシリウスディシジョン社の調査結果によれば、見込みがないと判断をして放置したリードの内、約8割は2年以内に競合他社で導入しているということがわかりました。
そのため、失注が決まっていたとしても、定期的なコミュニケーションを取り、再度検討する際に思い出してもらえるように関係性を維持していきましょう。
最後に
今回は、後追いメールについて解説を行ってきました。
後追いメールを行っている営業マンは多くいるとは思いますが、なんとなく行っている方も多いのではないでしょうか?
実際に、会社側から後追いメールまで指示するところは少ないと思いますので、ここは営業マンの技量による分野と思われますが、会社から後追いメールについてのルールを作ってしまうのも良いと思います。
そうすることで、他社に流れてしまったり、コミュニケーションが途切れて自社を忘れてしまったりすることもなくなり、成果へ繋がりやすくなります。
ぜひ、ご参考にしていただければと思います。